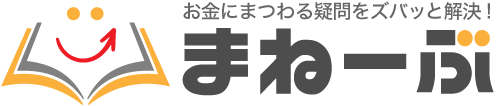株の初心者

ここ数年個人投資家として株取引をやり始めている人は増えています。
東京証券取引所の2017年個人株主数の調査によると、4年連続で個人投資家が増え続け、5,129万人に上ります。
このことから、株に対して興味を持つ人が増えてきています。
これから株を始めようとしている初心者の中には、
- 株をどうやって始めたら良いのか
- 初心者だけど株は難しいイメージがある
- 株で儲けるためにはどうしたら良いのか
等々のことを思っている方も多いと思います。
株について正しい知識を身につけ、きちんと情報収集すれば、初心者でもしっかり株の運用をすることができます。
そこで今回の記事では、「株」についての説明と実際に株の初心者が取引するための準備と初心者が気を付けるべきポイントをお伝えしていきます。
目次
「株」を買うと企業のオーナーになれる
株を買うということは、企業のオーナーになるということです。
企業は、新商品の研究・開発のための資金や、人を雇ったりする資金など、多くのお金が必要になります。そのため、出資者を募り、事業のための資金を集めます。
よく目にする「株式会社」の目的は、株式を発行することで出資者を募り、集めたお金で利益を上げることです。
企業に資金を投資した人を「株主」と呼び、株主に対する出資の証明書として付与されるのが「株式」になります。
株式投資をするには証券口座を開設
株式投資を行うためには、証券会社に株を取引きするための証券口座を開設する必要があります。
株の初心者の場合、ネット証券で口座開設することをおススメします。
取引手数料が安く、証券会社から銘柄の情報も見ることができ、パソコンやスマートフォン(スマホ)から素早く簡単に注文をだすことができるからです。
ここでは、証券口座の開設方法について解説をしていきます。
証券口座開設時に必要な書類をそろえておく
証券口座に申し込みをするにあたり、本人確認書類の提出が求められます。
なので、予め必要な書類を準備しておきましょう。
口座開設時に必要な書類
本人確認書類
以下のうち、どれか1つ
顔写真付き本人確認書類(免許証、パスポート、在留カードなど)
顔写真なし本人確認書類(住民票の写し、健康保険証(各種)など)
※氏名・住所・生年月日の記載があるものマイナンバー
以下のうち、どれか1つ
個人番号カード
通知カード
マイナンバーの記載された住民票の写し(有効期限は発行から6カ月以内のもの)
マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書(有効期限は発行から6カ月以内のもの)
ネット証券で申し込みをする場合、写真やスキャンをしてアップロードする形になります。
必要書類を揃えておけば、最短翌営業日に証券口座を開設することが可能になります。
初心者は特定口座(源泉徴収あり)で申し込みをする
初心者が申し込みの所で初めに迷う点として「特定口座」の選択だと思います。
証券口座には、「一般口座」と「特定口座(源泉徴収あり・なし)」の2種類があります。
初心者の人は、「特定口座」(源泉徴収あり)を選ぶと確定申告が不要になるのでおススメです。
その理由は、税金の納め方に違いがあります。
- 一般口座
税金の計算、納税まで全てを自分で行う必要があります。
- 特定口座
特定口座の中でも、源泉徴収「あり」か「なし」かの2種類に分けられます。
・源泉徴収「あり」の場合、納税時にやるべきことを全て証券会社がおこなってくれるので何もせずに納税ができます。
・源泉徴収「なし」の場合、証券会社が作成した年間取引報告書に基づき自身で納税を行わなければなりません。
しかし、株の初心者にとって証券会社を自分で選ぶのは難しいですよね。
取引に慣れていない株初心者の場合、少額での取引を行うことが多いです。
そこで、1日10万円までなら取引手数料が無料のネット証券をおススメします。

SBI証券では取引手数料のプランがあり、「アクティブプラン」にすると1日の約定代金の合計が10万までは何度取引しても手数料が無料です。
手数料が安く、取扱商品の数がネット証券の中では一番多いので初めて証券口座を持つ人、これから株をどんどんやりたい人におススメします。

楽天証券は、取引手数料プランの「いちにち定額コース」にすることで手数料を安く抑えることができ、1日の約定金額の合計が10万円以下は、手数料が無料です。
株の取引額に応じて楽天市場などで使える楽天スーパーポイントが貯まります。
既に楽天会員の人であれば、口座開設が最短30秒で完了します。

松井証券は1日の約定金額の合計が10万円以下であれば、手数料無料になります。
1日10万円以下であればいつでも無料なので、株を試しにやってみたい人におススメです。
証券口座に入金する際にネットから入金手続きをする銀行の提携先が多いので、スムーズに入金するができます。
利益になる3つのパターンで銘柄選びが変わる
株で利益になるパターンは3つ存在します。
- 1.値上がり益(キャピタルゲイン)
- 2.配当(インカムゲイン)
- 3.株主優待(インカムゲイン)
どのパターンを重視していくかによって銘柄選びが変わってきます。
初心者の方が銘柄を選ぶ際は、配当や株主優待などの「インカムゲイン」狙いから始めることをオススメします。
株式を保有しているだけで利益を得ることができ、配当や株主優待の価値が高い会社は株価も安定している傾向にあるからです。
そこで、3つのパターンがそれぞれどういったことなのか説明をしていきます。
1.値上がり益(キャピタルゲイン)
株価は毎日変動していますが、株価が安い時に株を買い、高くなった時に売ることで、その差額が利益になります。
この値上がり益のことを「キャピタルゲイン」といいます。
買った銘柄の株価が上がれば大きな利益を得ることができますが、思惑通りに行かなかった場合は損失が膨らんでしまいます。
2.配当(インカムゲイン)
配当とは、会社が稼いだ利益の一部が株主に還元されることです。利益の大きい会社ほど配当も大きい傾向にあります。
配当のように、株式を保有しているだけで得られる利益を「インカムゲイン」といいます。
配当金は1株あたりの金額がいくらと決まっています。
保有株数が多いほど配当金を多く受け取ることができ、安く株を買った人ほど「配当利回り」がよくなります。
- 配当金の計算方法
1株あたりの配当金 × 保有株数
例えば、1株につきA社から10円の配当が出たとして100株保有していれば「10円×100株=1000円」の配当を受け取れます。
- 配当利回りの計算方法
1株あたり配当額 ÷ 購入金額 × 100
例えば、A社の株を1株1000円で買っていたとして100株保有していれば「10円÷1000円×100=1%」の配当利回りということになります。
3.株主優待(インカムゲイン)
株主優待とは、企業が配当とは別に、株主に自社製品などモノやサービスを送ることです。
株主優待には、自社製品の他に、優待券やクオカード、家電製品、カタログギフトなど多くの種類があり、年に1回の企業や年2回優待を贈る企業があります。
株主優待も株式を保有しているだけで得られる利益なので「インカムゲイン」となります。
配当金や株主優待には、受け取る権利をもらう「権利確定日」という期日があります。
配当金や株主優待を受けるためには、3営業日前の権利付き最終売買日までに株を購入しておくことが必要です。
権利確定日は企業によって違うので、よく確認してください。
株式投資の醍醐味は「値上がり益(キャピタルゲイン)」にあります。うまくタイミングをつかんで上手に売買できれば、配当や株主優待とは比べものにならないくらい大きな利益を得ることができます。
しかし、その分損失になるリスクも大きくなります。配当や株主優待重視でも損失がでることがありますが、配当や株主優待を出す企業は、安定的な値動きをする銘柄が多いです。
そのためには配当や株主優待だけでなく、企業の業績が良い、売上や利益がしっかり伸びている銘柄を選ぶことも大切です。
株初心者の人は取り扱い銘柄が豊富なSBI証券の口座を開設しておくことをおススメします。

ネット証券の中でSBI証券は取扱商品数No.1です。
SBI証券では取引手数料のプランがあり、「アクティブプラン」にすると1日の約定代金の合計が10万までは何度取引しても手数料が無料です。
株の買い注文を出してみる
株の買い注文の方法は2種類あります。
- 指値(さしね)注文(値段を指定して注文)
- 成行(なりゆき)注文(値段を指定しない注文)
初心者の人は、基本的に現物取引の「指値注文」を使うようにしましょう。
成行注文では、いくらの値段で買えるかわからないからです。
ただし、「どうしてもこの銘柄を買いたい」という時は、成行注文を使います。
注文方法は慣れれば数秒でできるようになります。注文に必要な入力は次の3つです。
- 1.株数
- 2.値段
- 3.有効期限
株は100株単位なので、100株、200株、1500株など100株の整数倍で注文をだします。また、値段を指定します。以下の表をご覧ください。
| 売り注文 | 値段 | 買い注文 |
| 600 | 1003 | |
| 700 | 1002 | |
| 500 | 1001 | |
| 1000 | 500 | |
| 999 | 500 | |
| 998 | 1200 | |
| 997 | 1500 |
株には「板情報」があります。板情報を見れば、どの価格にどのぐらいの注文が入っているのかが一目でわかります。
左側が売りたい人がだしている「売り注文」、右側が買いたい人がだしている「買い注文」となります。
1001円には売り注文が500株でているので「1001円で500株」の買い注文をだせば約定(注文の成立)します。
一方、1000円以下で買いたい場合は、「998円で500株」の注文をだせば、買い注文として板情報に載ります。
1万円の少額からでも株取引ができる
株式投資に慣れないうちは大きい金額で株取引をするのは怖いですよね。
そこで、慣れるまでは少額でスタートしてみてはいかがでしょうか?
1万円の少額からでも株取引ができる制度を紹介します。
1万円から株を買うには、3つの方法があります。
- 単元未満株・・・1株から購入することが可能
- ミ ニ 株・・・1単元の1/10の単位での株式売買が可能
- 低 位 株・・・株価が100円を下回るような株
少額取引であれば、大儲けとはいきませんが、大損失を防ぐことができます。
まずは株取引がどういうものか慣れるという意味で、株が不安な人は少額取引から始めてみる事をおススメします。
少額取引について詳しい解説をした記事がこちらです。
少額投資に興味がある人はぜひ読んでみてください。
株取引には取引できる時間帯が決まっている
通常の株取引を行う場合は平日の朝9時~11時30分(前場)と12時30分~15時(後場)に行います。
休日は土曜日、日曜日、国民の祝日、年末、年始3日間(1月1日~3日)です。それ以外は上記時間帯で取引が行えます。
購入前に目標値を決めて株を売却する
購入前に利益となる目標の株価や、思惑が外れて下落した時に売る株価を決めておくようにしましょう。
始めのうちは、株価が10%上昇か5%下落したタイミングで売ることを目安にしてください。
常に株価を見続ける必要はありませんが、1日1回はチェックするのが理想です。
例えば、1,000円で購入していた株価が1,500円になったら利益確定の売り(利確)、800円を下回ったら損失確定の売り(損切り)と決めておきます。
1,500円には指値注文をだしておけば大丈夫です。ただし、800円を下回った場合には指値や成行注文ではリアルタイムに対応することができません。
そのような時は「逆指値注文」を利用するようにしましょう。逆指値注文なら「800円を下回ったら売り」という条件で注文を出すことができます。
初心者が知っておくべき株取引の3つの注意点
株初心者の場合、取引で大きな損失を出してしまったり、株取引のルールを把握していないことで、知らない内に犯罪を犯してしまう可能性もあります。
ここでは、初心者が知っておくべき注意点3つを説明していきます。
- 株初心者は信用取引をしない
- 株価が安い仕手株は買わない
- 株取引には金融商品取引法が適用
株初心者は信用取引をしない
株初心者は、「信用取引」をせずに、自己資金の範囲内で取引を行う現物取引で株の売買をするようにしてください。
信用取引では、実際に持っている資金以上の株を取引することができるので、損失をした場合借金になってしまう可能性があります。
信用取引には「信用買い」と「信用売り(空売り)」の2つがあります。
「信用買い」は、証券会社からお金を借り、自己資金の約3倍の価格の株を買うことができます。
「信用売り(空売り)」では、証券会社から株を借りてその株を売り、後から借りた株を買い戻して証券会社に返します。
信用取引は利益が出たときは大きいですが、損をしたときは反対に大きな損失となってしまうのでリスクの高い取引です。株の初心者はやらないようにしてください。
株価が安い仕手株は買わない
株初心者の人は、株価が安い銘柄を買ってみようと思う人がいると思います。
しかし、1株単位100円以下のような仕手株と呼ばれるような株価がとても低い株には手を出してはいけません。
仕手株とは?巨額の資金を持っている投資家が意図的に株を買い占めて売買を行い、株価を操作された銘柄
その理由は、倒産寸前の会社もしくは、業績不振に陥っている会社の可能性が高いからです。
業績不振に陥っている企業の株価は、業績回復の目途がたたない限り上昇する事はほぼありません。
ですから、株価がとても安いからという理由だけで購入しない様注意してください。
株取引には金融商品取引法が適用
株取引には金融商品取引法によって禁止されている行為があります。
禁止行為をしてしまうと懲役や罰金といった重い罰則や処分が科せられるので注意してください。
株取引での禁止行為
風説の流布(ふうせつのるふ)
株の相場や有価証券の価値を変動させる目的をもって、虚偽の情報をネットやSNSなど外部に流すこと。
虚偽の情報は、市場の信頼性・健全性を阻害し、実際に投資家が投資判断をする際に、誤認させてしてしまう可能性があるため。
違反者は、懲役、もしくは罰金を科される。インサイダー取引
企業の内部情報に接する立場の会社役員・従業員・大株主・取引先などが、会社の経営・財務など重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に内部情報を知った企業の株取引を行うこと。
違反した場合、個人は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または両方が課せられ、法人は5億円以下の罰金が科される。
つまり、銘柄に関わる嘘の情報を周りに広めたり、自社の有益な情報を他人に教えて自社株の取り引きをさせる行為は犯罪となるためやらない様にしてください。
株初心者におススメの証券口座

SBI証券では取引手数料のプランがあり、「アクティブプラン」にすると1日の約定代金の合計が10万までは何度取引しても手数料が無料です。
手数料が安く、取扱商品の数がネット証券の中では一番多いので初めて証券口座を持つ人、これから株をどんどんやりたい人におススメします。

楽天証券は、取引手数料プランの「いちにち定額コース」にすることで手数料を安く抑えることができ、1日の約定金額の合計が10万円以下は、手数料が無料です。
株の取引額に応じて楽天市場などで使える楽天スーパーポイントが貯まります。
既に楽天会員の人であれば、口座開設が最短30秒で完了します。